人生、山あり谷あり。誰にとっても人生上手くいってる時と、上手く行ってない時というのはあります。まあ山の時は人も集まってくるんでどうでもいいんですけど、肝心なのは谷の時です。こんな僕にも当然谷の時はありました。底が見えないような本当に暗い、獅子の子落としの深い谷に。。。
もうかれこれ大学に入って4年。入学した当時はまさか休学するとは思ってもいませんでした。本当に人生ってわからないものですね。。。ブログをやってこうして自己発信してるとすら思ってもいませんでした。。勿論4年前に浪人した時もそれは想定外の出来事だったわけで、色々な運が重なり合って今があるわけです。
最近はプログラミングだったり色々なことに手を出してきてるので、大学の友人からは「なんで文学部にしたの?」なんて聞かれることが往々にしてあります。一浪して文学部、ノンネイティブでTOEIC960取れる実力あるなら上位学部受かったんじゃない??と。。。
いやいや、文学部しか受からなかったんです。。(あと付け加えておくと文学部にちゃんと誇り感じてますよ笑←)。今でも受験のことを思い出すと胸がキリキリすることがあります。大学入ってから4年も経って受験の話をするのは流石に憚られますが(SNSに比べるとブログだから許されることってあると思うんです。ある程度政治的な発言含め)、実は慶應文学部は第一志望ではありませんでした。。。
ーー高校時代ーー
「最低でも早慶は受かる。東大を受けても恥ずかしくない成績だし、まあ受けてみろ!!」
三者面談で担任に言われた鶴の一声で、あっさり東大受験を決めます。まあ別に高校でも頭がいい方ではなかったんですが、英語と社会はできたし、自分でも一応粘り強く理系科目もやってきた自負があったので国立大学、その中の頂点である東大を目指すことにします。
そもそもうちの高校は当時は自称進学校みがあって、完全国立主義でした。実際に早慶受かっても千葉大だったり筑波大に行く人も少なくなくて、早慶に行く人はちょっとチャラチャラしてる、そんな印象すらありました。(生徒会長から慶應の魅力を高校で話せとか連絡きたので最近は変わったらしい)
まず先に結果を言うと東大は不合格。ここまでは自分でも納得の結果です。合格まで40点だったので惜しくもなんともありません。(そもそもうちの高校は東大特攻組が多いので当日は皆んなで写真撮ったりして観光気分だった)
早稲田文化構想学部 不合格
慶應義塾大学文学部 不合格
慶應義塾大学法学部 不合格
早稲田政治経済学部 不合格
上智大学(学部忘れた) 不合格
これは完全に想定外です。さすがに問題を解いていた手応えでも上智は受かった気はしていました。受験っていうのはわからないものですね。。(因みにうちのクラスはその年、自分より頭いいのも含めて早慶壊滅状態でした。)
浪人
浪人には2パターンあります。上を目指して浪人するパターンと全滅をして浪人をするパターン。自分は後者の方で、完全なる失意の中、受験後の3月、4月は浪人するか迷いながら過ごしました(センター利用で明治は抑えてた)。まあ、人生初の挫折と言ってもいいんじゃないでしょうか。
宅浪という選択肢もありましたが、何故かうちの高校は強制的に文系は河合塾に入ることになっていたのでその流れで何も考えずに河合塾に入ることになります。僕が通うことになった河合塾本郷校というのは東大専門特化校舎で、一応全員が東大を目指すことになってます。いわゆる受験プロたちが集まる校舎で、都内の進学校出身者が群れをなして群雄割拠しています。

クラスは東大アドバンス、東大プラス、東大無印の三つがあって、自己申告制だったが故に一番上のクラスに入ることにしました(さすがにガバガバでは)。まあ、数弱だったんで気持ちとしては東大プラスに入っても良かったんですが、自分より頭のいい連中の中に身を置く方が性格的に頑張るだろうと考えて一番上のクラスを選択しました。
クラスは70人くらい。全員が浪人生ということもあって東大合格率はあの鉄緑会を上回って全国一位なんだとか。7割が東大に行ける環境の中で当然自分も錯覚するわけですね。「あ、一年後、俺東大生かも。」と
ただ勿論そんなわけがなくて、4月早々、授業にはついていけなくなり、完全な落ちこぼれ学生としてクラスの後ろの方で内職を始めます。それでもかろうじて英語と地理、世界史だけはしがみついて授業を受けましたが、数学は一度も問題を解くことなく離脱しました。同じ高校で数学が得意だった女子がいたのですが、その子もついていけないとか言っていた記憶があるので、レベルはかなり上の方に照準を合わせてるとは思います。
校舎に通う生徒は基本的に全て浪人生ということでかなり特殊な環境ではあります。死んだ魚のような目をしてるもの、明らかに女の子のことしか眼中にない男子校出身者、自分より可愛い子の存在がどうしても許せない女子校出身者。拗らせつつも色んな考えを持つものが入り乱れます。
先生の方も浪人生に対するスタンスはさまざまで、「浪人は人生の汚点だ!特に女子はバツイチレベルの破廉恥だと考えろ」とかいう先生もいれば、「浪人というのは人生の財産!間違いなくこの一年は将来の糧になる」なんて言って励ます先生もいました。ただ講師はどれも超一流陣でした。(なぜか東○ハイスクールのCMに出てる先生とかが教えてた)
因みに当時、うちの高校の同じクラスからこの校舎には5人ほど通っていて、同じコース(クラス?)には3人いました。ただ3人ともザ・優等生タイプなわけで、自分はアウトサイダーというか夏期講習サボってカラオケ行って怒鳴られたりするような学生だったので、下手したら疎まれてるくらいの距離感でした。じきに真面目に授業を受けてる彼らの授業録音のおこぼれをもらいに行く以外に交流はなくなります。(うち1人は無事東大に受かって2019のミス東大ファイナリストになりました)
彼らは持ち前の社交性を活かして交友関係を広げるわけですが、そんな中自分だけがぼっちで友達もできず、羨ましくて、寂しくて、いつもお昼の時間はクラスの後ろで1人ご飯をかっこんでました。

ただそんな僕でも同じ匂いを感じ取ってか似たようなタイプの人に話しかけられることはあって(まあそれ以来話すことはなかったんだけど)、最初の授業の時には隣の男子とちょっと親しくなったりしました。因みにその人は現役で受かった慶應商学部を休学して浪人してるとのことで、英語には飽きたからドイツ語で受けるとかすごいこと言ってました。流石に東大受ける層は天井が突き抜けてるなあなんて感心したわけです。(ただその人は結局落ちたようで、翌年の生物の授業で偶然一緒でした)
色々カルチャーショックを受けつつも、それでも結局ぼっちなのは変わらず、自分の方でも友達をあえて作るようなアクションは取らなかったので基本的にはどこへ行っても1人でした。この友達がいないという環境が自分をあれほどまでに苦しめるとは、この時には想像もしていませんでした。
やがて、授業に意味も感じなくなったので、地下牢と呼ばれる自習室に行ったり

名前の通り地下にある。一切の電波遮断が売りだが、スマホ上に掲げて左右に振ると電波が入るらしい。
スカイラウンジと呼ばれる場所にこもって勉強するようになりました。

大手町の方まで綺麗に見える。ここにいる人は落ちるというジンクスがあって、実際に自分の年もそうだった。
そこでもなんとなく顔見知りができて話なんか聞くわけですが、東大の合格者数がうちの高校は毎回のように数え間違えてるだとか、東大に0.5点で落ちたとか、田舎の高校じゃありえないようなエピソードなんかも小耳に挟むわけです。
そんな都内有名進学校の知り合いも昼ごはんは高校の同期と固まって食べてるので、友達がいない僕は1人で外に食べにいきます。
文教シビックセンターって呼ばれる市役所に行ったり、

晴れた天気のいい日なんかは東京都戦没者霊苑でお弁当を広げて、時間いっぱい外で過ごしてました。

50分の休みがとてつもなく長く感じまして、鳩とか泳いでる錦鯉に残飯とかあげたりしてなんとか時間を潰してました。
そのうち、これ予備校通う意味ある?と疑問を感じるわけです。授業にもほとんどついていけないし、お互いを鼓舞しあうような友人もいないわけで、この辺りから完全なる独学に切り替えます(武田塾に行っとけばよかった)。チューターからも無視するように逃げ、チュートリアルと呼ばれる週一回のホームルームも出なくなります。
ただ塾に教えに来てる個性的な先生と話をするのは嫌いじゃなくて、授業には出ないくせにアフターみたいな時間によく雑談しに行ってました。特にガ○フィッシャーっていうイギリス人講師のところにはよく通ってて、当時は陰謀論に関する本を読んでたこともあって、フリーメーソンに入るにはどうすればいいですかとかいう至極くだらない質問を真面目に聞いたりしてました。(今どきフリーメーソンに入るくらいなら会員制ゴルフクラブの方がよっぽど役に立つぞと言ってました)。
予備校の授業に通わなくなると、せっかくの東京だし今度は予備校の周りを観光しようと、1人で色々なところに繰り出すようになります←親に予備校通ってないの知られたくないので東京には毎回出てた。あと普通に東京の空気が好きだった(田舎者並感)
水道橋とかドームシティのあたりは結構隈なく抑えてて、ラーメン屋とか定食屋は大体開拓しました。中でもダージリン春日店っていう水道橋にあるインド料理屋の店主とは実は結構仲が良くて、確か700円くらいだったんですけどよく遊びに行ってました。店主がインド人なんですけど、来日して30年近いらしくて日本で結婚して子供もいるようです。浪人という境遇もすんなり理解してくれて、「道のりがどんなに大変でも、結果を出せればそれでいい」的なことを教えてくれました。
コロナ禍で心配なので、水道橋行ったときには是非立ち寄ってみてください。(河合塾には合否伝えていってないくせにこのカレー屋のインド人店主には伝えにいきました。)
まあそんなこんなで、勉強もろくすっぽせずに遊び呆けるようになります。こんな生活をしていると、「ふと俺今何やってんだろう」みたいな感懐に囚われることがあります(これは休学中の今もたまに感じる笑)。これまではずっと何かしらの組織に所属してるわけで、今後の進路なり将来の方向性についてもとりあえずは先生だったり親の言うことを聞いておけばいいわけです。ただ浪人時代は今後の人生が全て自分の手にかかっているわけで、この状況下で自分のしてることはこれで大丈夫なのか?みたいな。どことも切り離された根無草のような自身の不安定な境遇にふと怖さを覚えることはありました。
一応夏の成績をまとめると、
英語:東大受験者平均くらい
社会:地理だけ合格者平均超えるくらい。世界史は平均くらい
国語:古文漢文壊滅
数学:壊滅
理科基礎:壊滅
まあこんな感じで判定もCでした。因みに小論は何故かできていたので、振り返ってみればこの頃から完全に慶應適性でした。
これはサンクコストってやつですけど、ここで私立専願に切り替えとくべきでしたね。やっぱりこれまで数学をやってきた自負(結構時間は費やしてきた)があったので、国立しか眼中になかったわけですが、ここで世界史と英語に振っておけばもうちょっと私大受験はスムーズにことが運んだと思います。後半事情があって勉強できなくなるわけですから。。。
やがて秋になると、せっかくできたサボり組の友人たちも塾に通わなくなり疎遠になります。まあ元々ラインを交換しないくらいの仲だったので友達と言えるほどでもなかったんですけど、これが徐々に自分の精神を蝕み始めます。
ついに発狂
夏の模試が返ってくると、塾の雰囲気もガラッと変わります。さすがは都内の進学校出身者。気合入れるときは気合入ります。9時近くまで自習室も満室になり、目に力が籠るようになります。授業も僕のように戦略的に切る人が増えてきます。
そんな中でこれまで費やしてきた数学の成績も伸びず、相談できる相手もいなくなったことで僕の精神はますます弱り始めます。この頃は半分勉強にも飽き気味で、何故か三島由紀夫の「金閣寺」をそのままノートに書き写すという謎の行為を始めます(受験生なのに余計なことを。。。)
三島由紀夫は元から好きだったんですけど、この写経を始めたきっかけとか動機とかが何故か記憶からはすっぽり抜け落ちてて、おそらく覚えてるかぎりこの辺りが最初の病みの兆候でした。
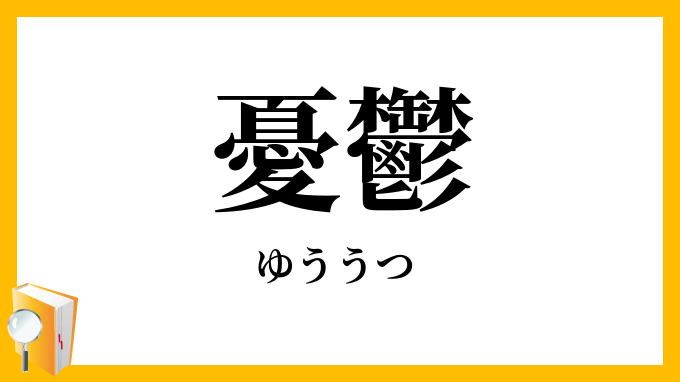
この病みの兆候はまず問題が解けないという実際的な問題に始まります。ゲシュタルト崩壊っていうやつでしょうか(例えば憂鬱っていう漢字をずっと眺めてるとその漢字が意味をなさなくなるようになるみたいな)。国語の長文とかを読んでいても一切意味が頭に入ってこない。不思議と読めないんですよ。同じ文章を繰り返し読んでも読んでも頭に入らなくてこんな状況が一ヶ月ほど続きます。続いて、読めないという状況から周りの音が気になり始めます。鉛筆の音とか、貧乏ゆすりの音に耐えられなくなって、問題を解いてる際は常に苦痛の時間でした。
友達がいないことも災いし、孤独感が一層自分を縛り付けました。元々孤独耐性はあると思っていたのですが、魔力のように「自分にだけ友達がいないこと」→「自分は完全に周りから否定されている」という短絡的な思考に絡め取られて思考の舵を奪われます。
さらに心の問題が肉体的な影響を伴うようにもなって、原因不明の足の痛みに襲われて杖をついたりしてた時期もありました(原因は本当に謎で、一応「偽痛風」という形で処理されましたが、体に異常はないので心因性で一過性のものだろうとのこと)。
さすがにここで自分でもやばいなと感じ、まずは河合塾のカウンセリングに向かうことにしました。カウンセリングというのは初めてだったんですけど、その方がすごい紳士的ないい人で親身になって話を聞いてくれました。本人もおそらく同じことで悩んだことがあることを伺わせるような、深い経験と知識に裏付けされた適確なアドバイスを施してくれました。実際にそのあとは一ヶ月くらい状態が改善し、家で勉強したり地元の河合塾に行って高校の友達と話したりなんかしました。ただ、じわじわと再び当時の「病み」の兆候は忍び寄ってきてて、ついにある夜発狂します。

大体11時くらいまで勉強して、朝7時くらいに起きるという生活を繰り返してたんですけど、急に夜、胸が締め付けられるような息苦しさを感じて飛び上がります。そこで親に「息するのが辛い。生きるのが辛い」そう吐露しました。
あとでわかりましたが、これは強迫性症候群といやつで、結構あるあるな病気です。小さい頃から付き合ってきたので、この病気自体を自分の性格の一部として当たり前のものと享受してましたけど、ここで初めて病名を与えられることで完治のきっかけを得ることになります。(これは幸甚としか言いようがない)
因みにこの当時は鉛筆の音とかそういうレベルじゃなくて、自分の心臓の音にも耐えられなくなっているような状態でした。鉛筆の音を防ごうと耳栓をしても、幻聴のようなものが常に聞こえるという状態で、一種のトランス状態でした。実際に経験したことがないとわからないと思うんですけど、麻薬とか吸ったらこんな景色でも見えるのかなーっていうレベルです。
とりあえずメンタルクリニックに行こうということになって(今は精神病院とは言わないらしいですね)、そこで症状を打ち明けました。メンタルクリニックというと大仰なものを想像するかもしれないですが、最近は結構人気があるらしくて僕の周りでも通ってる人はたくさんいます。精神的に辛くなったら早い段階で行ってみることをおすすめします。
そこでは一応、漢方を処方してもらうことで症状を抑えることになりました。合わせてカウンセリングみたいな形で臨床心理士とお話ししたりもしました。これでだいぶ症状は改善しましたが、そんなこんなで勉強するどころではなくなります。年明けにかけて二ヶ月くらいは精神の養生に努めました。
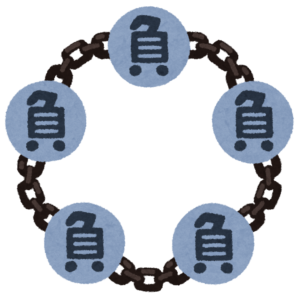
ただ精神は安定したんですけど、肝心の勉強の方が覚束なくなって、「勉強しない→焦る→焦ってさらに勉強できない」みたいな形で結構負のループにハマりつつありました。袋小路に迷い込んだネズミみたいで一応机には向かってはいたんですが、生産性はほぼ0でした。
ただこの二ヶ月間が後の人生に与えた影響は小さくないと思ってて、例えばこの時やっていた「金閣寺」の写経だったり、本を読み漁ったりした経験が文学部生としての今に繋がってると思うし、受験という努力とは切っても切り離せない状況下であえて休養を取ったことは、勉強の本質的意義についても否応なく考えさせられることもありました。おそらくこの時の経験がなければTOEIC960もプログラミングもなかったと思います。大学に入ってできることになる友達の重要性も、この時があったぶん骨身に染みてわかるような気がします。(仲間の重要性は本当に骨を削るようにして覚えました。)
そんなこんなで大学では文学をやりたいと考えるようになりました。ここについても結構書きたいことはあるんですけど、書き出したらメルヴィルの『白鯨』並みに長くてまとまらなくなるので割愛します。とりあえず早慶の文学部、ただ文学だけだと受験の幅が限られるので同じく文字体系を扱う「法学部」も受験することにしました。
年明け早々に行われたセンター試験では、なんとか790点を取ることができ、初志貫徹、東大文科3類に出願します。現役時にはセンター740くらいだったので、1年間浪人した成果はあったようです。
2月 いざ受験
早稲田文化構想学部 不合格
この不合格という言葉を見た時に、やばいと悟りました。私大の対策を全然してなかったのです。数学の結果だけに囚われて大して時間を割きませんでした(過去問もほとんど解いてない)
慶應法学部 不合格
現役と合わせてここまでくると、パソコンで「合格」という文字を見ることは一生ないんじゃないかと思うようにすらなりました。想像できないんですよね、受かった自分というのが。そこで唯一残った慶應文学部の結果はあえて見ずに、背水の陣で東大を受けることにします。
前日に最後の追い込みをかけていると、12時ごろにチャイムがなりました。特段気にかけてもいなかったのですが、後ろから父親が「慶應合格。これで慶應ボーイ!」と言ってくれたのを覚えています。(奇遇だけど父も一浪して慶應文。第二外国語まで一緒!)。なんとパソコンで合否を見る前に合格通知が大学から届いたのでした。まさに青天の霹靂。前日の正午で大学から送られてくるなんて知りませんでした。その瞬間体からは一気に力が抜け
ふう、俺の受験終わった。。。。
翌日受けた東大は結果として80点で落ち、慶應に進学することが決定しました。
もう一回言います。「80点」です。現役で40点で落ちたのにも関わらず倍以上の差分を開いて落ちました。1年間東大を目指してきた意味。。。先ほどサンクコストの話をしたのはそういう意味です。。最初から東大じゃなくて私大を目指しとけばよかった笑。ま、こんなの結果論ですけどね。
1年間付き添ってくれた高校の先生には申し訳ですが、「もう何も言わないでください」とだけ言って合否と成績開示を送った記憶があります。
(申し訳なかったから一応落ち込んでる演出したけど、当時はもう早く大学に通いたくて仕方がなかった。)
おわりに
まあこれらの個人的な経験から何か読者が糧とできるような形で普遍的な教訓を抽出するとすれば、「谷」の底の部分を知ることの強みでしょうか。。。この時は僕自身、結構精神も参ってたし、先が見えない中で悲観的になることも多くありました。何をやっても上位互換がいるわけでそこと比べると自分の存在意義ってなんだろうと。
一つ言いたいのは、
過去の出来事はどんなに美化してみても、醜化してみてもその過去に裏切られることはないということです。
これはもちろん恋愛なんかではデメリットとなって自分を苦しめることもありますが、正確にその時の感情を推し量れない分、印象によってその過去の出来事は強化されます。例えばその後の人生で辛いことがあっても「あの時の経験よりは・・・」という形で自分の中で最後の砦として持っておけるし、僕の中ではあの浪人の一年が最も大変で辛いどん底だったと考えれば、その後の人生に対してもある程度楽観的になることができます。
確かに大学に入ってからも辛い出来事には何度も見舞われましたが、その時は決まって本郷から水道橋のあたりを1人で歩いて「まだ大丈夫」と自分に言い聞かせてます。これで気持ちが入れ替わらなかったことは一度もありません。
ただ過去の出来事に対する解釈はいくらでも開かれてるわけで(事実は一つでも)、過去をどう捉えるかは性格にも起因すると思います。大切なのは谷に陥った時に腐らないこと。一度、谷の底に陥っても、自分ならできると信じて前を向き続けることで再起できるかがどうかが鍵だと思ってます。
谷が深ければ深いほどそれは強みになるでしょうし、一度自身の生存に対する危機感を覚えてしまえば、怖いものなんて基本的にはありません。他人からの批判、大切な人やものを失う怖さ、将来に対する漠然とした不安、こうした恐怖も谷の底を見たからこそある程度楽観的にもなれます。(楽天的とは違う)
おそらくあそこで第一志望の東大に行けたらまた違う人生だっただろうし、ましてや現役で早慶に行ってたら180度違う人生だったと思います。僕自身、慶應で出会った友人や教授の方々(特に英米文学専攻!)にはものすごい感謝してて、もし通ってる大学が慶應じゃなかったら…と思うとゾッとするくらい幸運な出来事にも恵まれたりもしました。(慶應は遊ぼうと思ったらいくらでも遊べるし、勉強しようと思ったらいくらでも勉強できる本当に素晴らしい学校です!!!)
今の自分にとって浪人の経験は絶対に必要なものです。4年前に戻って「浪人するか」と聞かれても、おそらく浪人するだろうと思います。谷の底の部分を知ったこと、そこから再起したこと、そして楽観的になれたこと。この3つはやはり何にもまして誰にも奪えない自分の強みです。
まあ、人に偉そうなことを言える立場ではないんですが、この個人的な経験を普遍的な形で締め括るとこんな結論になるかなあと思います。長くなったし、いい感じでまとまったのでここら辺でブログは終わりにしようと思います。(あ、9000字も書いてしまった。。。)

